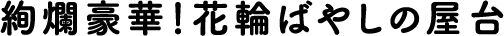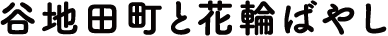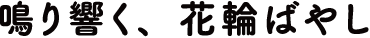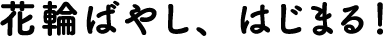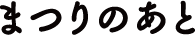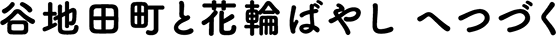毎年、8月19日、20日、秋田県鹿角市花輪地域で行われる「花輪ばやし」。「産土神さん」と呼ばれ地域の守り神として親しまれている「幸稲荷神社」にお囃子を奉納する祭礼行事です。
祭りの2日間は、夕方から明け方を中心に、躍動的なお囃子を奏でながら屋台が町じゅうを練り歩きます。その荘厳な姿から「日本三大ばやし」ともいわれ、平成26年には国の重要無形民俗文化財に、そして平成28年には、日本の「山・鉾・屋台行事」の一つとして、ユネスコの無形文化遺産にも登録されました。
今月は、この絢爛豪華な夏祭り「花輪ばやし」について学んでいきます。
7月16日。花輪ばやしの開催まで約1ヵ月という時期にやってきたのは、道の駅かづの。ここにある「祭り展示館」には、花輪ばやしに参加する10町内の屋台が保管、展示されています。ここで、今回講師となっていただく、谷地田町の佐藤俊さんにお話を伺います。


- 佐藤
- これらは祭りで実際に使っている屋台です。祭り以外の日は、ここに来ていただければ、屋台を見ることができますよ。
- 矢吹
- よく見ると、各町内ごとにデザインが違っているんですね。
- 佐藤
- そうですね。作られた年代も大きさも違いますし、元々は宮大工さんが作っているので、その大工さんの腕前によっても違っているんでしょうね。
- 矢吹
- ピッカピカですね。
- 佐藤
- 金色の部分は金箔ですね。ベースの黒い部分は漆です。

- 矢吹
- 漆塗りなんて、今だったら考えられないことですよね。
- 佐藤
- 全部修繕するとなると、数千万円はかかってしまうのでね……。
- 矢吹
- 各町内でお金を出し合ってやってきたっていうことですよね?
- 佐藤
- そうなんですよ。現在、鹿角市の人口は3万人ちょっとですが、かつて「尾去沢鉱山」が稼働していた頃は人口が5〜6万あったそうで、花輪の町も買い物や飲み食いする人たちで、経済的にも潤っていたんですよね。

- 矢吹
- お祭りには、全部で10町内が出るんですね。谷地田町の屋台はどれですか?
- 佐藤
- 実はうちの町内のものは、いまここにはないんです。平成26年に国指定の文化財になったこともあり、屋台修理事業が行われることになって。なので、谷地田町の屋台はいま、お色直し中なんです。
- 矢吹
- そうなんですね!


- 佐藤
- 町内によっては、傷みの激しい屋台もあるので、この事業で数年かけて少しずつ修理していく予定なんですよ。初年度は、現存しているなかで一番長い期間修理していなかったうちの町内の屋台をやってもらえることになりました。
- 矢吹
- いつ以来の修理になるんですか?
- 佐藤
- 昭和39年に作ってから全く修理していなかったので、50数年ぶりになりますね。いま屋台は建設会社にあるので、そこに見に行ってみましょう。
修理中の建設会社へ


- 佐藤
- こちらです。ここ、おそらく漆が塗ってあるんで、気をつけてくださいね。今回は土台の部分を中心に、屋根、あとは柱にもヒビが入っていたので、そういう箇所を修理しているところです。上も見てみましょうか?
- 矢吹
- わ〜! 屋根を間近で見られるなんて! 貴重な体験ですね。

- 佐藤
- 私も初めてですよ! いつも下から眺めているだけですからね。屋根の合板は張り替えている最中ですね。この屋根の側面の装飾部分を「破風」というんですが、うちの町内のは特徴的で前後左右4方向にあるんですよ。他の町内は前後2方向なんですが。柱も8本と、ほかの町内より多くなっています。


- 矢吹
- へ〜! 破風にあしらわれたモチーフ、これはキツネですね。こちら側は鳳凰……。やっぱり縁起ものや華やかなものが使われるんですね。
- 佐藤
- うちの町内は竜が好きなのか、柱には竜が彫られていますね。浴衣にも竜が使われているんですよ。木は主に欅と桂を使っているそうです。屋根の上には鬼板という飾りが付くんですが、いまは外されていますね。本来はものすごく立派なものが付くんですよ。いや〜それにしても、きれいになってますね〜!!


- 矢吹
- ここに、太鼓はいくつぐらい乗るんですか?
- 佐藤
- 町内によって様々ですが、うちは前4つ、後ろに5つになりますね。さらに、そこに三味線と笛も加わって……。全部で15人くらいが屋台に乗りますね。

- 矢吹
- 賑やかな屋台になるんでしょうね!
- 佐藤
- はい。そして、花輪ばやしの屋台は「腰抜け屋台」といって、中に穴が開いていて、囃子方はその中で歩きながら太鼓を叩くんですよ。その屋台を提灯を持った人たちが先導していくんです。

- 矢吹
- となると、みなさんは、ずーっと歩いていないといけないんですね。
- 佐藤
- そうなんです。でも実は、うちの町内だけは去年までこの穴の部分に網がついていたんですよ。それに乗って太鼓を叩いていたので、歩かなくてよかったんですが、この修繕を機に、元のスタイルに戻して網を外すことになったんですよ。網に乗っていたほうが、正面から見たとき、叩き手の顔が見えて、かっこよかったんですけどね……。
- 矢吹
- 少しずつスタイルを変えながらも、これを長年維持していくっていうのは、なかなか大変なことですね。
- 佐藤
- 非常に貴重な財産ですからね。修理する技術を持った人も少なくなってきているでしょうし。昭和39年にこの屋台が完成したときに、その前に使っていた古い屋台の破風や土台は他の町内に譲ったんですよ。そこから、祭りに参加できるようになった町内もあるんですよ。
- 矢吹
- いいお話ですね! そうやって祭りを広げてきたんですね!


花輪ばやしの屋台の、貴重な修理現場まで見せていただけた私たち。次回は、佐藤さんの町内「谷地田町」を訪ねて、祭りの見どころを伺っていきます。