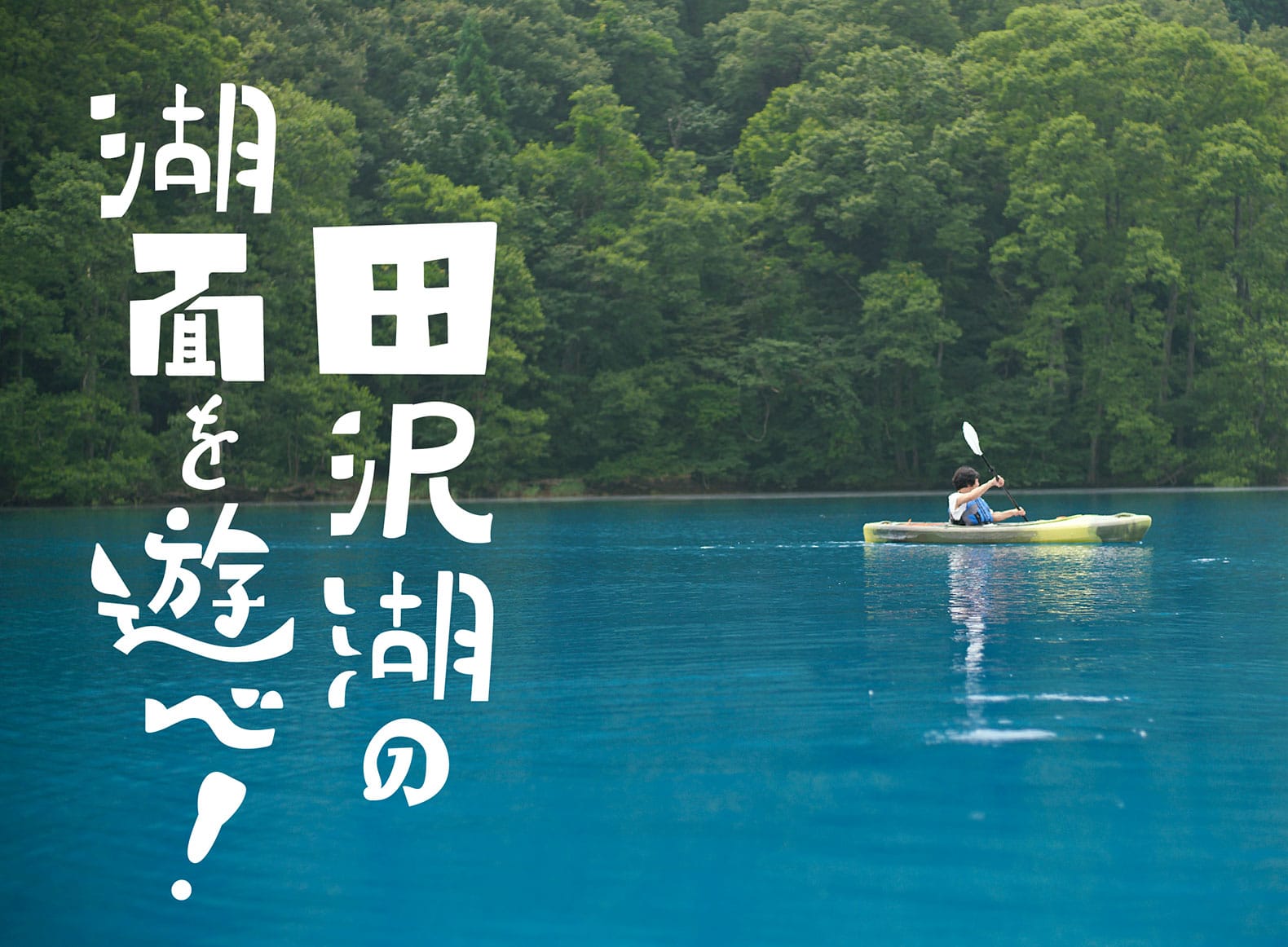Babahera Ice: 1. Off to the Babahera Factory!
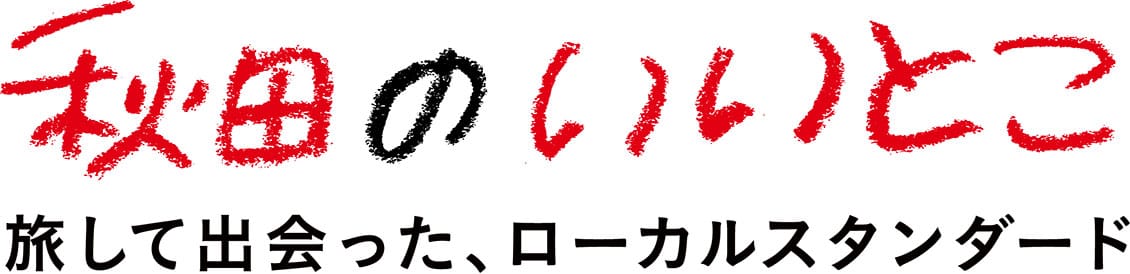

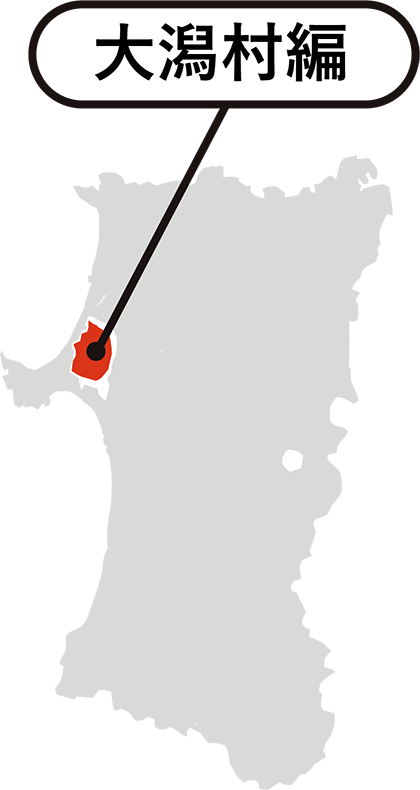
文:成田美穂 写真:高橋希
おいしさの決め手は “握り” ?
秋田土産の定番「パンプキンパイ」の加工場に行ってきた
2019.05.22
みなさん、JA大潟村の「パンプキンパイ」を知っていますか?
大潟村産のかぼちゃで作った餡を、バターたっぷりの生地で包んで焼き上げた手のひらサイズのパイで、
「秋田に行ったら必ず買う!」
「初めて食べたけど、すごくおいしい」
「毎日食べたいくらい好き」
「実家からの仕送りに入ってるとテンション上がる!」
などなど、SNSでもファンの声が多くあがる人気のお菓子。秋田県内の道の駅や空港、駅の構内、スーパーでも販売されており、お茶の間だけではなくお土産としても親しまれています。


今回は、その背景に迫るため、パンプキンパイが作られている「大潟村加工センター」へお邪魔しました。

こだわりのかぼちゃ餡


- パンプキンパイは、「かぼちゃ餡」と「生地」のふたつからできています。そのレシピは、発売当初からずっと変わっていないこだわりのものです。


- 加工センターでは、お盆明けから約1カ月半かけて、その年に採れたかぼちゃをペースト状にして冷凍保存します。このペーストが、かぼちゃ餡のもとになります。
餡を作る時は、このペーストを釜で煮詰めて溶かしながら、白餡、砂糖、卵黄、生クリームなどを入れて味を整えていきます。そして、1時間半ほどかけて水分が飛ばしながら固めていきます。


- 塊になったペーストを専用の機械に投入すると、同じ大きさ、同じ重さにカットされて出てきます。これが、できたてのかぼちゃ餡です。
——ちゃんとパイ一個分になって出てくるんですね! すでに甘くておいしそうな香りがします。

- 大潟村を代表する農産物のひとつ「くり大将」は、その名の通り、栗のようにホクホクとしていて、ほどよい甘さが売りです。それに、収量も安定しています。
実は、以前は別の品種を使っていたんですが、生産者さんたちから「もっと収量も品質も良いものを使おう」という声があがり、数年前にくり大将に変わりました。

——年間でどれくらいのかぼちゃを消費するんですか?

- 村内の農家さんから仕入れている分で、年間約30トン。それをペーストにすると量が半分になるので、かぼちゃ餡としては約13〜15トンになります。
かぼちゃの半分は、皮や種、ワタでできていますが、パンプキンパイには「実」の部分しか使いません。つまり、1個のかぼちゃからパンプキンパイになるのは、全体の半分程度なんです。

——実以外の部分は捨ててしまうんですか?

- いいえ、廃棄はしません。村の農家さんたちが引き取って、畑の肥料として使ってくれています。
——かぼちゃ丸ごと、余すところなく使われているんですね。
パンプキンパイは、香りが命!

- 餡の次は、パイ生地です。ふだん、この大きなミキサーを使って生地を練っています。





——生地からほんのりバターの香りがしますね。

- このバターも、発売当初からこだわっているものです。 実は数年前、ずっと使い続けていた北海道産のバターが全国的に入手困難となったため、輸入バターを使ったらどうかという話があったんです。


- もちろん、お菓子によっては輸入バターが合うものもあります。しかし、パンプキンパイの生地にとって大切な要素である「香り」は、北海道産バターでなければ出すことができません。
ですから、それが足りないのであれば、手に入った分しか作らない。常にそういう覚悟でいます。

パイを「握る」?

- 餡と生地の準備ができたので、ここからパイを握る作業に入ります。
——パイを「握る」、ですか?

- かぼちゃ餡を生地で包んでいく作業のことです。ここだけは、機械を使わず手で行ないます。
パンプキンパイの魅力である「素材をいかした手づくりの味わい」は、やはり機械では出せないと思うんです。これも、発売当初から変わらず続けていることです。





——すべて機械で大量生産されていると思っていたので驚きました! まさに、「握って」いましたね。

- この作業、一見簡単そうに見えますが、非常にコツがいります。うまくやらないと、このあとプレスした時に、餡がはみ出てしまうんです。素早さはもちろん、丁寧さも大切です。



- オーブンで焼き上げたあと、包装してダンボールにつめたら出荷準備完了。だいたい3日以内には各店頭へ並びます。

——ひとつずつ手づくりということですが、これは一日に何個くらい作るのでしょう?

- ここ最近は、年間で約30万パック。ということは、5個入りなので150万個のパイが売れています。つまり、一日平均で5,000個、つまり1,000パックですね。それを、9〜10人で作っています。
生産量を増やすこともできますが、お客様にご迷惑をかけることなく作ること、そして、従業員への負担が大きくなりすぎないことを考えると、これが私たちの身の丈にあった数だと思っています。あくまで、無理のない範囲で。
愛され続ける理由

——このパンプキンパイはいつごろ誕生したのでしょうか?

- 販売が開始されたのが平成元年なので、今年で丸31年になります。
もともと大潟村は、日本農業のモデルとしてつくられた土地でしたが、昭和50年代から、お米以外にかぼちゃやメロン、麦や大豆などの穀類を作り始めました。
もともと湖底だった大潟村の土壌は、ミネラルが豊富に含まれていて、かぼちゃの栽培に適していたそうなんです。
その後、昭和60年代頃に入ると、村で採れた農産物に付加価値をつけようという動きが始まりました。そんななか、かぼちゃの売り先を広げるために、大潟村の加工特産品第一号として開発されたのが、この「パンプキンパイ」でした。




——31年間作り続けてきたレシピと、素材をいかすための手づくりへのこだわり。この「変わらない」味こそ、パンプキンパイが愛され続ける理由なんですね。

- 発売当初は、新規取引先の拡大など、苦労したこともたくさんあったそうです。
しかし、全国各地から入植された村の皆さんがそれぞれの故郷へ送ったり、かぼちゃの品質を追求し続けたり、村の加工特産品として大切にしてきたからこそ、長く愛される商品になったのだと思います。
弟分の「くろまめパイ」も伸ばしていきたいところですが、いちばんはやはり、パンプキンパイの品質を大切に維持していくことですね。これからも、たくさんのかたに食べていただきたいです。

【パンプキンパイに関するお問い合わせ】
〈事業所〉あぐりプラザおおがた
〈住所〉南秋田郡大潟村字中央1-5
〈時間〉9:00〜19:00
〈TEL〉0185-45-2214