廃校を買い取って15年
廃校の利活用といえば、国も地方も民間もいまや積極的に推し進めているトピックですが、約15年前、県外から藤里町へ通っていたひとりの女性が中心になって、廃校になった校舎を買い取り、現在にいたるまで維持・活用を続けているという…
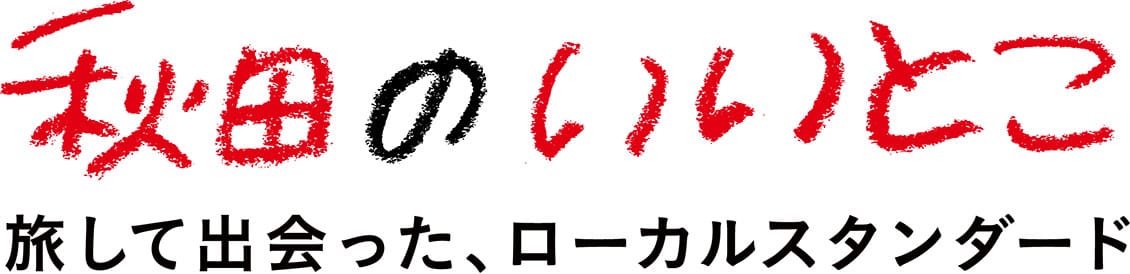

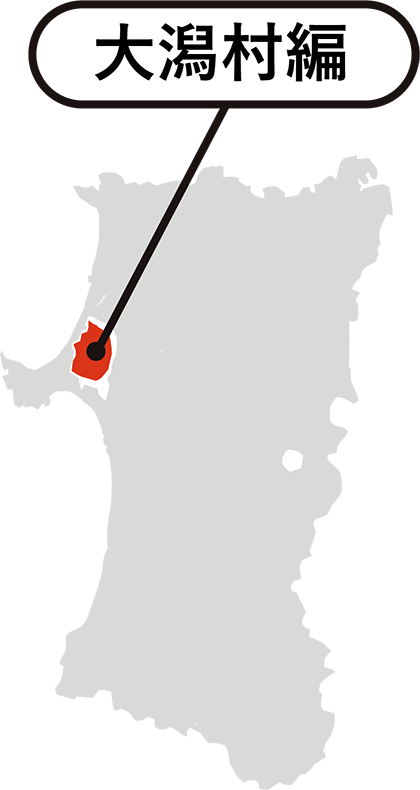
編集・文:矢吹史子 写真:船橋陽馬
2019.05.29
「農醸」という日本酒があります。これは、「農家がつくる日本酒プロジェクト」という企画から生まれたもので、米が種の段階から日本酒になっていくまでの過程をみんなで共有し、味わおうというもの。
この酒を注文した方は「メンバー」となり、年3回にわたりできあがった日本酒が届けられ、さらには限定のコミュニティに参加できるなどの特典を得ることができます。

今年で7年目になるというこのプロジェクト。2019年5月19日。ちょうど、今年の田植え体験が行われるということで、この酒米を作っている「大潟村松橋ファーム」を訪ねました。







この日の体験をすべて終えたところで、「農醸」のプロジェクトについて、松橋拓郎さんにお話を伺います。

——松橋さん、お若い印象ですが、おいくつですか?

——就農されたのは?

——このプロジェクトは2013年に始まったということですから、就農されて2年目には始められたということですね?


——就農して間もないころから、すでにこのプロジェクトのイメージがあったんですね。


——それが、実際にプロジェクトになったのには、どんな経緯があったのでしょう?




——そういうなかでできた一年目のお酒は、どういうものでしたか?



——みなさん、何もなくても、これから動き始めるワクワク感があれば十分だったのかもしれませんね。




——どういうことですか?






——考え方がしっかり届けば、これについて語れる仲間が240人もいる、ということにもなりますからね。




——それぞれのなかで充実感が深まっていく、というような?

——ある行程を担う一人、というような?



「農家がつくる日本酒プロジェクト」
http://noukanosake.strikingly.com/