小坂鉄道レールパークで、懐かしの時代へトリップ!
小坂鉄道は、小坂町と大館(おおだて)市を結ぶ旧鉄道路線。かつて鉱産額が日本一だった小坂鉱山の貨物輸送のために生まれました。明治42年に小坂鉄道株式会社が設立され、旅客事業がスタート。長きにわたり活躍したものの、鉱山が閉山…
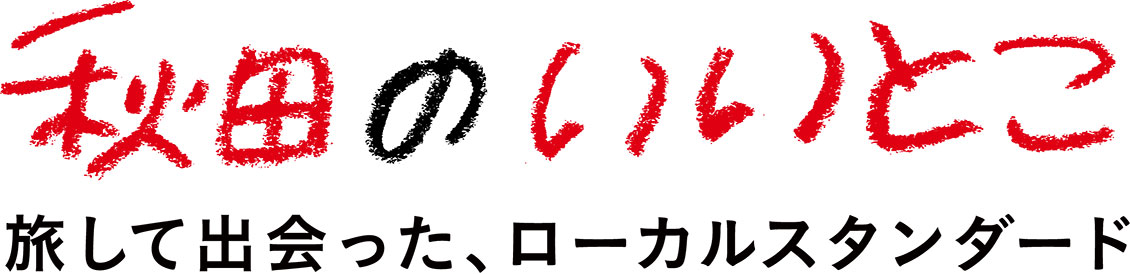

文:成田美穂 写真:高橋希
2019.06.26
秋田県で2番目に面積が小さいまち「井川町」。
人口約4,600人のこのまちに、「県内初にして唯一」と呼ばれる学校があると聞き、早速やってきました。

それがこちら、「井川町立井川義務教育学校」です。
あまり聞き慣れない「義務教育学校」とは、いったいどんな学校なのでしょうか?




——6年生で「卒業」するのではなくて、7年生に「進級」するんですね。なんとも不思議な感覚です。





——ここができる前は、町に小学校や中学校はいくつあったんですか?


——でも、義務教育学校という新しい制度を取り入れるのは、町としても大きな決断だったのでは?

——小中一貫教育が学力向上につながる、ということですか?


——へえー! 確かに、中学校にあがった途端に授業のやりかたが変わって、最初は慣れるまで大変だった記憶があります。授業時間も長くなりますし。



——なるほど。9年間続けて教えることで、変化や成長も見えやすいかもしれませんね。


——なるほど。先生の負担もおのずと増えてしまう……。



——小中一貫で教育するということは、先生同士の連携が大切になってくるんですね。


——ここでは、6歳から15歳までの子どもたちが同じ校舎にいるんですよね。統合前と比べて、生徒のあいだで何か変化はありましたか?




——先生とは違う視点でのアドバイスがもらえそうで面白いですね。





——そういう意味では、縦のつながりって大切ですね。9つの世代が同じ空間で毎日過ごすってなかなかないので、貴重な経験だと思います。


——この学校は、たくさんの「つながり」のうえに成り立っているんですね。


——さらに少子化が進むであろう秋田にとって、地域ぐるみで子育てや教育に取り組む姿勢は欠かせませんね。

【井川町立井川義務教育学校】
〈住所〉南秋田郡井川町坂本字山崎38
〈TEL〉018-855-6012