トージ!・コージ! 〜福禄寿酒造編〜
「発酵デザイナー」という肩書きを持つ麹(コージ)のプロフェッショナル、小倉ヒラクさんが、秋田の酒蔵を訪ね、酒造りのリーダーである「杜氏(トージ)」にお話を伺うこの連載「トージ!・コージ!」。今回は、秋田市から車で北へ約4…
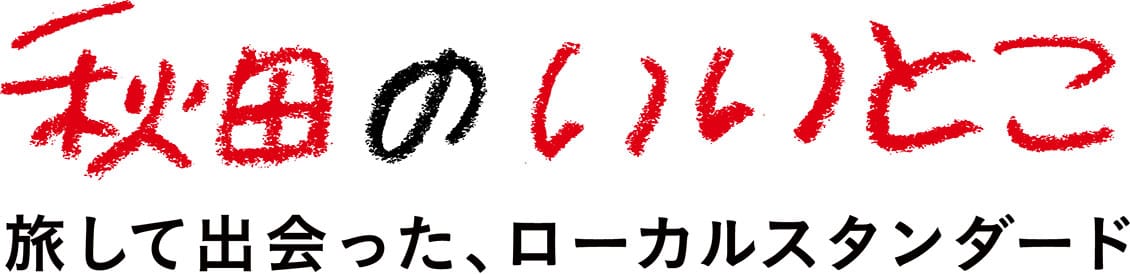

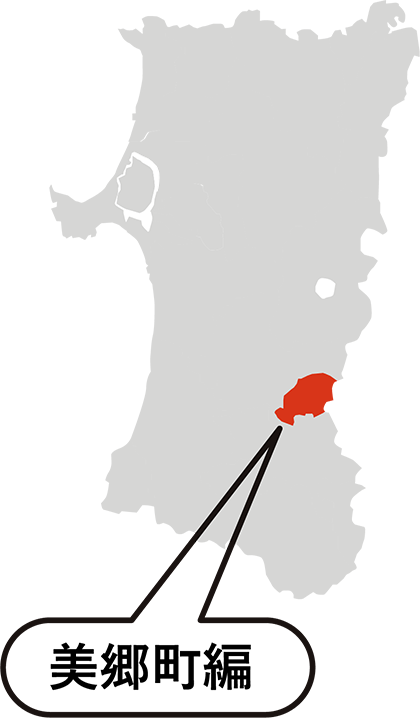
編集・文:矢吹史子 写真:高橋希
2019.07.17
「納豆は、つぶ派? ひきわり派?」
秋田の人たちにそう聞くと、その多くが「ひきわり」と答えるかもしれません。それを裏付けるかのように、秋田のスーパーの納豆コーナーには、ひきわり商品が大充実。県外の方に「秋田はひきわり天国だ!」と言わしめるほど。
そんな、秋田のひきわり納豆の文化のルーツはどこにあるのでしょう?
それを探るべく、美郷町にある「ヤマダフーズ秋田工場」を訪ねました。


この日、案内してくださったのは、ヤマダフーズ広報課の小西恭司さんです。

気になるひきわり納豆の話題の前に、まずは、秋田の納豆の歴史をお話いただきました。そこで紹介されたのが、この一枚の絵です。





——ぷ〜ん、と……。

——よく食べましたね……。発酵したのは、馬の背中に乗っていたからなんでしょうか?

——米俵に入れて馬に乗せていたことが功を奏して納豆が生まれたんですね。


ここからは、パネルで解説していただきながら、ヤマダフーズとひきわり納豆のあゆみを伺っていきます。




——え〜! 家みたいですね。今の工場とはだいぶ違いますね。

——パネルに「夫婦二人三脚」とあります。山田清助さんが、奥さんとで始められたんですね。


——いいパッケージですね。



——昔ながらの作り方に科学的な考えを取り入れていったんですね。

——それはなぜなんでしょう?



——それでも敢えて、ひきわり納豆を売り込んだんですか?

——清繁さん、攻めてらしゃいますね!



——900年前に秋田で発祥したときのものは、つぶの納豆だったと思うんですが、いつごろからひきわりの文化が生まれたんでしょう?

——へ〜!!




——発酵させる前に割っているということすら知りませんでした。大きな大豆を発酵させてから割るのかな、とも思ったり。自社で割ることで、鮮度の高いものにできるということなんでしょうか?


——まんべんなく蒸されるような仕組みになっているんですね。



——ヤマダフーズさんのひきわりへの情熱が、これだけ強いものだとは思いませんでした。私はいつも「極小粒」という商品が好きでよく買っていたんですが、これからは、ひきわり派になってしまいそうです。



——小西さんは、やっぱりひきわり派なんでしょうか?


——わ〜〜〜〜! 入れません! 小西さんは入れるんですね?

——知人も、納豆に砂糖を入れるというのでびっくりしたら「だって、甘い豆と米なんだから、おはぎと一緒じゃない?」って言われたことがありました……。

——県南出身の編集部のスタッフも、「給食の納豆に砂糖が付いてこなくて不思議だった」と言っていました。秋田の人たちは、甘いのが大好きなので、お赤飯にもお砂糖を入れたりしますからね……。

取材後、小西さん流、砂糖入りひきわり納豆に挑戦してみました。


食べてみると、恐れていたほどの拒絶感はなく、ふだん食べているものよりまろやかな印象。梅の酸っぱさも効いていますが……さすがに毎日は無理そうです(笑)。
砂糖を入れるかはともかくとして、古くから秋田の人々の暮らしのそばにあるひきわり納豆。そのルーツを知ることで、もともと大好きだった納豆が、さらに誇らしいものになったように思えます。
【株式会社ヤマダフーズ】
〈住所〉仙北郡美郷町野荒町街道ノ上279
〈TEL〉0182-37-2246
〈HP〉http://www.yamadafoods.co.jp/