小坂鉄道レールパークで、懐かしの時代へトリップ!
小坂鉄道は、小坂町と大館(おおだて)市を結ぶ旧鉄道路線。かつて鉱産額が日本一だった小坂鉱山の貨物輸送のために生まれました。明治42年に小坂鉄道株式会社が設立され、旅客事業がスタート。長きにわたり活躍したものの、鉱山が閉山…
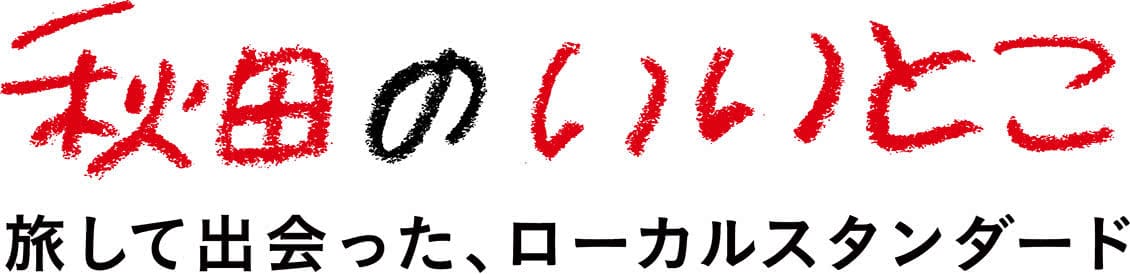

編集・文:矢吹史子 写真:高橋希、上小阿仁村教育委員会
2019.11.20
上小阿仁村八木沢集落に継承されている伝統芸能「八木沢番楽」。
番楽とは、秋田と山形のいくつかの地域に伝わる山伏神楽の一つ。太鼓、笛などの伴奏に合わせ、数種類ある演目を順番に舞うことで、悪霊を払い、天下太平、五穀豊穣を祈願するといわれています。
地域によって、節や踊りは異なるものの、その多くが、お盆から秋にかけて行われ、番楽の日には集落の集会所などに舞台が設けられ、子どもから大人までが酒や食べ物を持参して集まり、演技を楽しみます。

「八木沢番楽」もその一つで、200年以上の歴史があるといわれていますが、第二次世界大戦の際に演じ手不足のために一時中断。その後復活を遂げ、1982年には村の無形民俗文化財に指定されますが、1989年頃、後継者不足によりふたたび途絶えてしまいます。
しかし、そこから20年経った2010年頃に再度復活。その後は上小阿仁小、中学校の生徒たちによって継承されています。

今回は、この八木沢番楽について、八木沢番楽保存会会長の佐藤敏雄さんにお話を伺います。佐藤さんは現在94歳。子どもの頃からこれまで見続けてきた八木沢番楽とは、どんなものなのでしょうか。
——佐藤さんは、何歳から番楽を始められたんですか?

——では、16歳になってから番楽を覚えた?




——子どもの頃は「早くやってみたい」と憧れていたものですか?

——その当時は、番楽をやる人は集落にたくさんいたんですか?


——歌詞が書いてありますね。





——八木沢番楽は、何度か途絶えながらも、10年ほど前に復活したとのこと。





——それでも、みんな踊れるようになった?



——最近は、先輩から後輩へ、子どもたち同士で教え合っていると聞きました。




時代の変化にともなって、伝統文化の継承の形が変わっていくのは逃れられないことであり、かつてよりも厳しい状況のようです。 しかし、継承の原動力となるのは、いつの時代も、その文化への憧れや関わる人の熱量、その土地への愛情であり、それは、変わらないことなのかもしれません。その原動力をどう生み出していくか、どう持続させていくかを問われているように感じました。