ここまで手造り?!「シバタ焼肉のたれ」が育んだもの。
朱色で書かれた「焼肉のたれ」の文字。無骨なパッケージを開けて、ひと舐めすると、パッケージに負けない力強い第一印象! でもそのあとに、辛さ、酸っぱさ、香ばしさ、まろやかさ……さまざまな印象が繊細に口の中を駆け巡り、最後には…
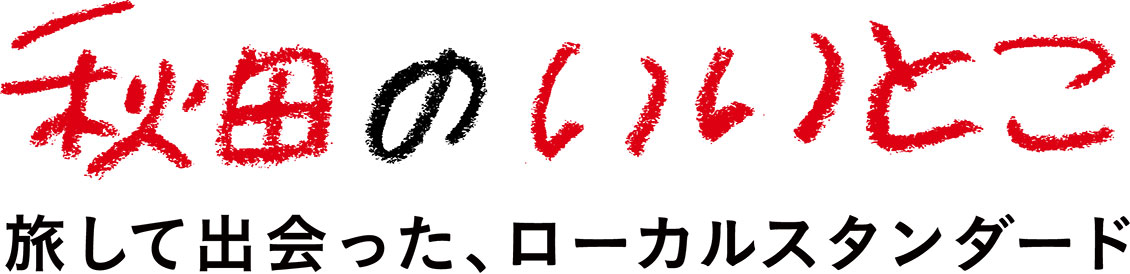

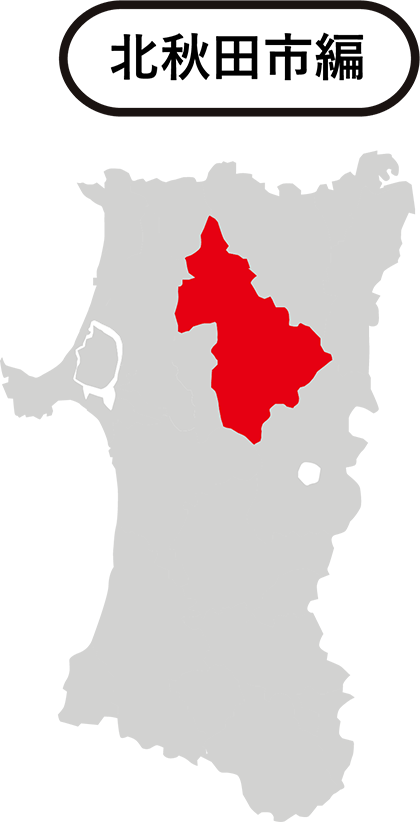
編集・文:矢吹史子 写真:高橋希
2020.01.15
北秋田市根森田地区。住民は28世帯80人という小さなこの地区に、「ORIYAMAKE」というゲストハウスがあります。
ここは、織山英行さん、友里さんご夫婦が営む宿。2018年にオープンし、約2年が経ちますが、これまでの宿泊客の約7割が外国人。
今回、このORIYAMAKEを訪ねてお話を伺ったところ、このように外国人が利用する宿になるまでには、織山さんたちによるさまざまな試行錯誤があったことがわかりました。そしていま、この宿を軸に、周辺地域や自然環境が循環しはじめているんです。








ここからは、英行さん、友里さんにお話を伺っていきます。




——はじめから、外国人向けの宿にしようと考えていたんですか?


——外から認められてはじめて気付くことってありますよね。


——外国人がお客さんとなると、大変なことも多いのでは?


——言葉はどうされているんですか?


——アクティビティも用意されているんですよね?



——英行さんは、マタギでもあるんですよね?

——鈴木英雄さんのように、山を楽しんでいる方もいるのに……。



——こういった取り組みに興味のある外国人も多そうですね。

【ORIYAMAKE】
〈住所〉北秋田市根森田字仲ノ又131
〈HP〉https://www.oriyamake.com/