「そのままでいいんだよ」。年齢差50歳のバンド?!ウキヤガラボーイズ!
秋田県大潟村(おおがたむら)は、1964年、日本農業のモデルとなる農村を作ることを目指して、日本で2番目に大きい湖だった「八郎潟(はちろうがた)」を干拓して作られた村です。
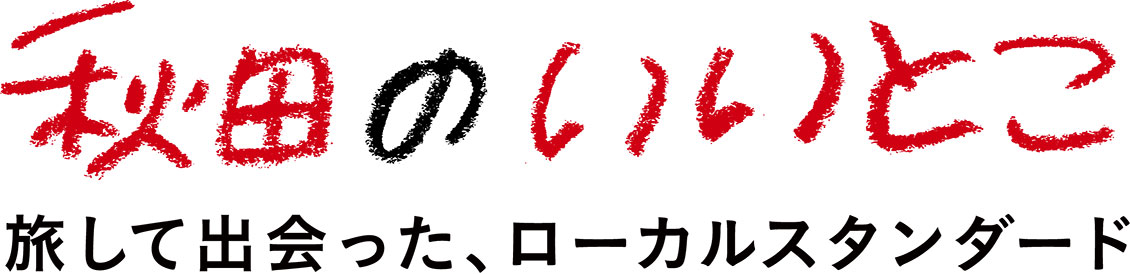


 椅子の向こうに見る景色
椅子の向こうに見る景色 あふれんばかりの、冷めることなき愛。
あふれんばかりの、冷めることなき愛。 精巧精緻・愛嬌満載
精巧精緻・愛嬌満載 不妊治療の未来を変えるために
不妊治療の未来を変えるために 「TO〜」あなたは何を描く? ビール、料理、建築の「TO〜MART」オープン!
「TO〜」あなたは何を描く? ビール、料理、建築の「TO〜MART」オープン! なくてもいいもの?
あきたタウン情報がつくってきた、たくさんの「きっかけ」。
なくてもいいもの?
あきたタウン情報がつくってきた、たくさんの「きっかけ」。 見えない物語を魅せる。アウトクロップ・スタジオ、始動。
見えない物語を魅せる。アウトクロップ・スタジオ、始動。 アニメの現場改革を、秋田から。
アニメの現場改革を、秋田から。 あなたを死なせない。「秋田モデル」が守るいのち。
あなたを死なせない。「秋田モデル」が守るいのち。 誰かの「こうしたい」に寄り添って。あくび建築事務所。
誰かの「こうしたい」に寄り添って。あくび建築事務所。 甘酒が咲かす、糀のチカラ。あまざけらぼ。
甘酒が咲かす、糀のチカラ。あまざけらぼ。 ブレンド米という知られざる世界への誘い。
ブレンド米という知られざる世界への誘い。 いつでも竿燈を楽しむひとつの方法。
いつでも竿燈を楽しむひとつの方法。 もっきり天国、土崎で100年以上続く酒屋を教わりました。
もっきり天国、土崎で100年以上続く酒屋を教わりました。 大森山動物園のいいとこをいくつもあげていきます。
大森山動物園のいいとこをいくつもあげていきます。 まさにノーミュージックノーライフ。 ホソレコで音楽再発見。
まさにノーミュージックノーライフ。 ホソレコで音楽再発見。 コーヒー&カセットのマイペース。
コーヒー&カセットのマイペース。編集・文:矢吹史子 写真:高橋希
2021.01.06
先日、なんも大学で取材をした「沼山大根」。長い間、その栽培の歴史が途絶えていたものの、数名の生産者の手によって復活を遂げたという伝統野菜です。
2020年、この大根にまつわる短編映画『沼山からの贈りもの』が完成しました。
これは、秋田市にある国際教養大学の学生が在学中に制作したもので、さらに、この制作をきっかけに、彼らは「株式会社アウトクロップ」を立ち上げ、秋田を拠点に動き出そうとしています。
オフィスである「アウトクロップ・スタジオ」を訪ね、代表の栗原エミルさんにお話を伺いました。

——『沼山からの贈りもの』は、いつ頃撮影されたものなんですか?

——この撮影、どのようなきっかけで始まったんでしょう?


——「学生時代の記念」のような思いから始めた撮影ということですが、長期間携わるなかでなにか変化があったんでしょうか?




——この『沼山からの贈りもの』を全国で上映するために、現在、クラウドファンディングをされているそうですね。


——映像の、その先を体感してもらう。これは、沼山大根の生産者さんをずっと見てきたからこそできる発想ですよね。沼山大根を通して、本当に大事なことに行き着いたような。

——そこから起業するまでに至るというのも、すごい展開ですね。



——思いを同じくした仲間に出会えたことも大きいのでは?


——二人とも、同じように伝えたい何かがあって、その手段として、映像というものに同じようにたどり着いた。

——先ほどの、「遠くまで行きたいならみんなで行く」という言葉、とても素敵なんですが、栗原さんにとっての「遠く」というのはどういうものでしょう?


——結果的に、一人で行くよりも早く着くということにもなりそうですね。

——これから、どんなことを大事に制作をしていきたいと思っていますか?






——沼山大根もその一つだった?





——そういうものに寄り添いたいと感じるのは、なぜなんでしょう?



【株式会社アウトクロップ】
https://www.outcropstudios.com/