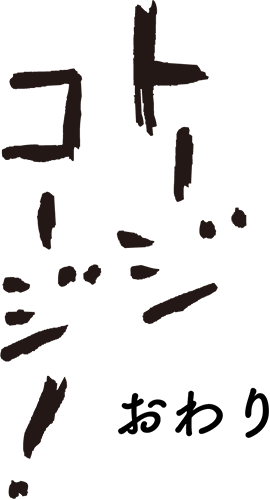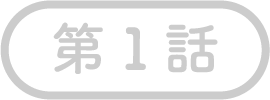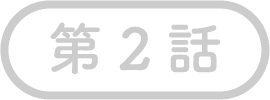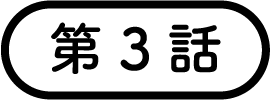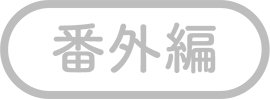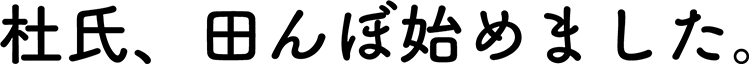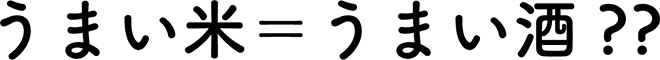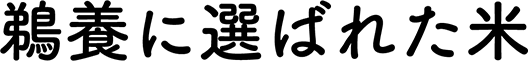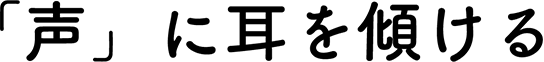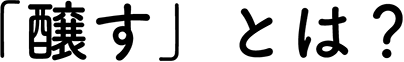第3話
秋田の「新政酒造」の杜氏、古関弘さんと、「発酵デザイナー」小倉ヒラクさんによる対談。
最終話では、古関さんが挑戦し始めた米作りについてのお話を入口に「発酵とは? 醸すとは?」の本質が見えてきます。
(この対談は、2017年6月に行われたトークイベント「トージ・コージ」をもとに再編集したものです)
古関弘さん
1975年秋田県湯沢市生まれ。富山県で日本酒の世界に入り、32歳で新政酒造に入社。37歳で杜氏となり、全国的にも注目を集める「新政」の酒造りの中核を担う。現在は、新政酒造の「農/醸一貫化」を果たすべく奮闘中。
小倉ヒラクさん
発酵デザイナー。「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、東京農業大学の醸造学科研究生として発酵を学びつつ、全国各地の醸造家たちと商品開発や絵本・アニメの制作やワークショップをおこなっている。2017年に『発酵文化人類学』(木楽舎)を出版。

- 古関
- 冒頭(第1話)で「杜氏でございました」と言ったんですが、2017年から、新政酒造がお米作りをすることになりまして……。
太平山の麓の、秋田市河辺岩見三内というところの一番上流「鵜養地区」っていう、日本昔話みたいなものすごくきれいな所にうちの社長が目をつけまして(笑)。そこで酒米を作って、その米で酒を造りたいっていうのがうちの社長の夢なんですね。
そしたら「新政の最大戦力を投入することに決めた!」とか言うもんで、「いいね!」って思っていたら「5年で形にするから、古関、おまえが農業やれ!」って言われて(笑)。
- 一同
- はははは!

- 古関
- 実家は「川連漆器」の職人の家で、畑も田んぼもやってなくて、鉢植えすらしたことのない僕が、今、そこに移住させていただいて、使われていない家を借りまして……。嫁さんが「どうぞ」って言ったので、僕一人で……。
- 小倉
- 単身赴任だ!


- 古関
- ……まあ。そんな、ものすごくきれいな所で米を作って、近い将来「無農薬の酒米の里」っていうのを実現して、そこに新政の新しい蔵を作りたいと思ってるんですよ。その蔵も鵜養の木を使って作って、そこの茅で茅葺きの屋根にして、そこの杉で木の桶を作って。そして、そこで造るお酒は、鵜養の酵母だけを使って、そこの米だけで造るっていうのが僕らの次の夢なんです。
- 小倉
- うん。いいね!

- 古関
- とにかく、ものすごく歴史のある地域なんで、そこに混ぜていただいて、地区の人たちのお力を最大限にお借りしながらやってるんですよ。
- 小倉
- 愛知県に「澤田酒造」っていう小さな蔵があって、僕、仲良しなんだけど、この前「ヒラクさん、新作できたので飲みに来てください」って言われたので行ってきたんですよ。完全無農薬の「雄町」っていう、結構育てにくい酒米で醸した酒を、吟醸酒のようには米をたくさん削らずに、米の旨味を活かした酒だったんですけど、それが、腰抜けるほどうまくて。
そしたらそこのお母さんがね、ニヤニヤしながら「お米がうまいと酒がうまいのよね」って。これって一見、当たり前のようだけど、じつは、酒蔵からその言葉って、なかなか出てこない。日本酒はやっぱり「米」よりも「造り」の方がでかいから。
- 古関
- うん。

- 小倉
- お米の段階だと、どういう酒になるかはわからないのね、全く。だからお米ができて、そのお米から麹を起こして、今度は酵母くっ付けて……っていう中で、だんだんお酒の味が決まっていく。だから「米がうまいから酒がうまい」っていうのは結構すごいことなんだよね。
一方で、ワインを造ってる人ってみんな「ワインはほぼ農業です」って言うんですよ。どういうブドウを作るかっていうことで、ワインの味が7〜8割決まるんだよね。でも僕、最近は何周か回って「やっぱり日本酒もワインと一緒なんじゃないかな」って思い始めているんですよ。やっぱり、原料のお米と水でお酒のキャパシティって決まってくるんじゃないかなって。
新政って今までは、そこにいる「菌」でブレイクスルーを起こしてきたんだけど、次のブレイクスルーは「原料の米自体のクオリティ」のところにいくんじゃないかな。

- 古関
- 日本酒だけじゃないけど、米のとりまく評価の在り方って「品種」ありきなんですよ。コシヒカリが美味しいから、みんなコシヒカリを栽培する。コシヒカリを栽培するためにいろんな工夫をする。でも、僕は「鵜養が選ぶ米」を作りたいの。
- 小倉
- その土地が選ぶ。
- 古関
- うん。鵜養の土地が選んできた米を作りたい。それでね、僕が勝手に「鵜養師匠」って呼んでる師匠が88歳、米寿のお父さんなんだけど……。
- 小倉
- 米みたいな人だね。
- 一同
- ははは(笑)

- 古関
- その師匠に「師匠の子どもの頃ってビニールハウスもなかったし、どうやって米作ってたんですか?」って聞いたんです。そしたら「確かに、農薬もない時の米作りは大変だけど、病気がねがった(なかった)」って。
- 小倉・一同
- 小倉・一同うんうん。
- 古関
- それで、「その当時使っていた米って何ですか?」って言ったら「アイカメ」だって。「アイカメはいがった。あんまり量はでぎねぇけど、うめがったな。病気にもなんねがったし、丈も伸びねぇがら、倒れねがったな」と。
それで、うちの蔵のハイテク若者イケメン軍団に「アイカメって言ってたから調べろ!」って言ったら、次の日、ハイテク若者イケメン軍団は、ちゃんと米の系統図を出してきて。
「アイカメ」っていうのは、「愛国」っていうのと「亀の尾」の間の子、それで「愛亀」っていうんですね。正式な名前は「陸羽132号」というんですけど、その米は寒い東北にフィットしたんですね。鵜養の人たち、鵜養の土地が選んだ米が、愛亀だったっていう。
- 小倉
- うん。

- 古関
- それ、じつは宮沢賢治が……宮沢賢治って作家だけじゃなくて農業指導員だったんですよね。その宮沢賢治が、「やませ」の吹く岩手で「米作るためにみんなこれやりなさい」って言ってたのが、陸羽132号なんです。
- 小倉
- 宮沢賢治のお米ってこと?!
- 古関
- そう!
- 小倉
- それで酒造るってこと?
- 古関
- それが僕の次の夢です。
- 小倉
- ロマ~ン!
- 一同
- ははは(笑)

- 古関
- 鵜養の土地が選んだ米を、最高にうまい米に栽培して。癖があったっていいんですよ。その癖を魅力に変えるために僕らの技術があるから。僕らがその米の力を最大限引き出していく。最高の酒を造るために僕らは勉強をしてきているし、そのために酒蔵で働いてきたからね。
- 小倉
- うん。
- 古関
- そして、これはあくまで僕の夢なんですが、僕は愛亀の圃場を鵜養一面にバーッと作って、それで、鵜養の木で蔵を作って、そこでもう一回杜氏に戻りたいなって……(笑)。
- 一同
- (拍手)
- 古関
- ありがとうございます!

- 小倉
- 宮沢賢治の『狼森と笊森、盗森』っていう森の話があるんだけど、そのなかで、百姓が土地を開墾する時に森に向かって「ここの木、もらっていいか?」って問いかけるのね。そしたら森が「いいぞ」って言って木を切るっていうシーンがあるんだけど、これって今の僕たちからするとファンタジーなんだけど、現場の人たちからするとリアリティーがすごくあると思っていて。
発酵文化が本当にそうなんだけど、やっぱり「自然と人とのコラボレーション」なんだよね。そのコラボレーションの中でいい関係性が作れると、おいしい発酵食品が作れるっていうことだと思っていて。
でも人間は「自分の言うことを一方的に向こうに聞かせる技術」っていうのを発達させすぎてしまった。それはそれで効率は良くなるんだけど、最高にうまいかどうかっていうと結構微妙……。
- 古関
- そこなんだよ……。

- 小倉
- 「とりあえず70点」のものじゃなくて「最高のもの」を目指すために大事なのは、もう一回、僕たちが森に向かって「この木をもらっていいか」って言ったときに、向こうが「いいぞ」って答えてくるのを聞き取れるかってことなんだよね。それが、百姓には聞こえてるんだよね。そして古関さんにも「菌の声」が聞こえてる。それがやっぱり素晴らしいなって思っていて。
さらに、古関さんは今、田んぼの声を聞こうとしてるけど、その土地が選んだお米を使うことって「その土地の言うことに耳を傾けて、その土地がいいって言ってるものを選んで、きちんとフェアな関係でコラボレーションしましょう」っていうことだと思っていて。僕は、そこから始まるものをベースに経済や文化を作っていくのが、これからの地域のあり方だと、すごく思ってる。

- 古関
- きっと「醸す」って「あるものを好きになる」ってことなんですよね。そこにある人とそこにあるものを、うまく転がすのに参加するのがきっと「醸す」っていうことで。だから僕、今は農業をしてるけど、全然「醸してる」と思いたい。
- 小倉
- うんうん。
- 古関
- そういうとこに行きたい。きっと、新政の蔵人たちと酒を造ることも、米を作ることも、地域の人と何かをしたいっていう意思で動くことも、全部「醸す」ことだと思っていて。「杜氏」の字ってさ、「木」と「土」なんですよね。
- 小倉
- うんうん。あ、本当だ。

- 古関
- 農業もきっと木と土だし、だから杜氏って「醸すことが仕事」だとすると、僕、農業っていう場で杜氏として全然、醸してるんじゃないかなって。
- 小倉
- いや、でも、本当にそのとおりで「関係性を整える」っていうことだと思うんですね。よく「発酵って究極、何ですか?」って言われた時に、「時間をかけて良くすること」っていうふうに言っていて。ポイントは「時間をかける」っていうことなんだけど、急いでやらないで、然るべきタイミングで、然るべき時間をかけて物事を良い方向に導いていくっていうこと、それが「発酵」だと。そういう時にポイントになるのは「関係性」で。
良い関係性を発見して、その関係性を適切な時間をかけて温めていくっていう。そういうことで生まれてくる、醸し出されていくものっていうのが、いい文化を作るんじゃないかなって思う。

- 古関
- 僕、妙に自信があって。人も物もみんなちゃんと良くなるようにできてるって信じてるんですよ。だから「気持ちいいね」って僕が感じてあげて「ああ、気持ちいいな」って誰かに言ってあげるだけで、元々の良さが回り始めるんですよ。それが、20年酒造りをしてきて教えてもらった、一番のことかもしれないな。


ここからは、対談後に古関さんから伺ったお話です。この対談に登場したキーワードが一つに繫がっていきます。
古関さんのチャレンジ、そして秋田の日本酒は、ますます面白くなっていきそうです。

調べていくうちにわかったんですが、愛亀っていうのは、昭和30年以前からある米で、日本で最初の人口交配の米らしいんです。東北の寒さにも強い「亀の尾」と、いもち病に強い「愛国」という米を掛け合わせてできたのが「愛亀」なんですが、この愛亀の世代までは、お米って化学肥料に対応していなかったんですよ。肥料を入れなくても良いお米が穫れていた。でも、収量が少なかったんです。実際、愛亀に肥料を使ってみたら、丈が伸びすぎて倒れて収穫できなかった。

それで、愛亀の次の世代からは、収量の多い稲を作ろうと、肥料を入れて丈を伸ばしても倒れない稲を作ったことで、それまでの2倍以上穫れるようになっていったんです。でも肥料を入れるっていうことは、農薬とセットになってしまう。つまり、収量は少なかったけど、無農薬の稲としての最高傑作は愛亀だっていうことなんですよ。

もともと僕は、無農薬に適した米でやりたいと思っていたし、何より、その最高傑作である愛亀は「鵜養という土地が選んだ米」。
しかも、愛亀は大正10年〜昭和25年くらいまでの稲なんですよ。その頃というのは新政の黄金期なんです。6号酵母が出たのが昭和10年で、その酵母で造ったお酒で日本一になったことで、6号酵母が全国に伝わっていったんですね。そして、その当時使っていた麹菌は「カテゴリー1」。
6号酵母、愛亀、無農薬、カテゴリー1……。黄金期と今やりたいことが全部繫がっちゃった。

その愛亀の種も手に入ることになって、2018年の春から使っていくんだけど、まだお酒を造るほどの量は穫れないので、1年かけて種を増やしていこうと思ってます。
さらに、ヒラクさんからも、
対談を終えてのメッセージをいただきました。
「現代の目で、自然を見つめ直す」
これからよりステキな発酵文化を育んでいくために必要なのは、古関さんのような視点だと思います。
日本酒醸造の世界は、ここ数十年のあいだ「なるべく自然の不確定性を減らして標準化する」ことを目指して技術を磨いてきました。それはお酒の平均レベルを上げるために大事なことだったと思うんですね。

そして今、全国の日本酒の酒質はものすごいクオリティになりました。
そこから先を目指すために、今度は「もう一度自然の不確かさに向き合う」というステップが必要になってきているように感じます。
それはお米や微生物とどのように向き合うかというスタンスの話であり、同時に不安定に揺らいでいる自分自身の感性に向き合うことでもあります。

金八先生みたいにアツい新政の酒づくりの現場は、未来の発酵文化が醸されていく場所なんだと思います。
古関さん、また続きをやりましょうね。