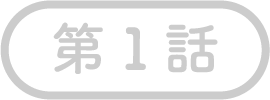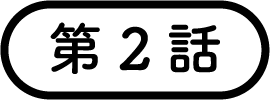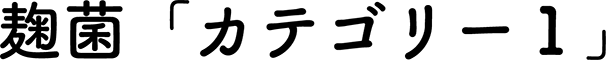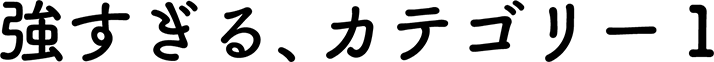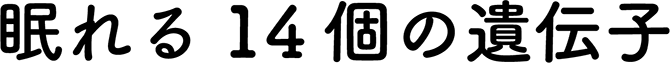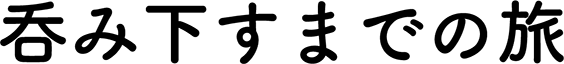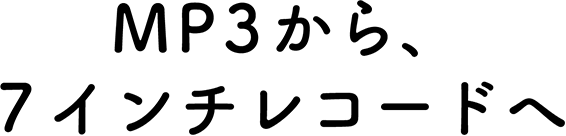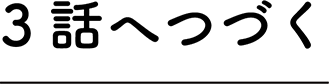第2話
秋田の「新政酒造」の杜氏、古関弘さんと、「発酵デザイナー」小倉ヒラクさんによる対談。今回は、古関さんが世界一おいしい日本酒を造ろうとするなかで出会った、ユニークな麹菌についてのお話です。
(この対談は、2017年6月に行われたトークイベント「トージ・コージ」をもとに再編集したものです)
古関弘さん
1975年秋田県湯沢市生まれ。富山県で日本酒の世界に入り、32歳で新政酒造に入社。37歳で杜氏となり、全国的にも注目を集める「新政」の酒造りの中核を担う。現在は、新政酒造の「農/醸一貫化」を果たすべく奮闘中。
小倉ヒラクさん
発酵デザイナー。「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、東京農業大学の醸造学科研究生として発酵を学びつつ、全国各地の醸造家たちと商品開発や絵本・アニメの制作やワークショップをおこなっている。2017年に『発酵文化人類学』(木楽舎)を出版。

- 小倉
- 新政の蔵に行った時に「鑑評会」っていうお酒の審査会に出した、古関さん入魂の一作を呑ませてもらったんですけど、僕、呑んで5秒くらい黙っちゃって「……ちょっとこれ、とんでもない酒造りましたね」って言ったら、「じつは、ちょっとヤバい麹菌見つけちゃって」って。今、新政は特殊な酒造りをしていることは、お話ししたとおりなんだけど、そもそも「菌の種類」が違うんですよね?
- 古関
- うん。今の日本酒って、みんなおいしいですよね?
- 一同
- うんうん。

- 古関
- 日本酒って、基本的にアルコールをつくる「酵母」と、お米を溶かす「麹菌」からなってるんですね。それで、酵母の話でいうと、今の日本酒っていうのは、じつはみんな新政から出た「6号酵母」の孫とかひ孫とかの、ハイテクな人(酵母)たちからできてるんですね。
そのハイテクな時代のなかで、うちの蔵には「日本で一番古い酵母を使って、世界で一番うまい酒を造れ」っていう命題があるもんだから、いっぱい工夫してきているんですけど「酵母を選べないなら麹で遊ぼう」ということで、いろんな麹菌を使い始めたんですね。
*6号酵母は、現在使用されているなかで最も古いものとなる。
そのなかで出会ったのが……え〜「とある麹菌」(笑)。ごめんなさい、ちょっと名前は伏せさせてください! これで造ってみたら……うまいんです。

- 小倉
- 全然違う?
- 古関
- 生き物として、違う! 理屈じゃない。……と、その詳しい話の前に、麹菌の歴史について、お話させてください。

- 古関
- 日本酒の起源が西暦700年くらいって言われてるんですが、当時から使われていたとされる麹菌を「カテゴリー1」とします。日本では、麹っていうのは、お味噌も、みりんも、お醤油も、漬物も、お酒も、みんな、西暦700年からこの1種類の麹菌だけで作られてきました。これが1955年まで続いてきたんだけど、戦後に分岐点がやってくるんです。
1955年を境にできたのが「カテゴリー2」と「カテゴリー3」に分類される麹菌。カテゴリー2は主に調味料。そして、カテゴリー3は、今のほとんどの日本酒に使われている麹菌です。
なんでこういうふうに分かれたかっていうと、カテゴリー1の麹菌って、変色するんです。もろみ(米が発酵しているけれど漉されてない状態のもの)そのものと酒粕が、灰色になってしまう。およそ食べ物の色に見えない色になるんですよ。
- 一同
- え〜〜!

- 古関
- それで、カテゴリー2や3がなんでできたかっていうと、酒と酒粕の色が濃くならない。しかも、コントロールしやすくてマニュアル化に向いてた。
西暦700年から1955年まで、何でも作れちゃう麹菌でずっと技術を蓄積してきたのに、「変色する」っていう一個の理由だけで、日本人は別の便利なタイプの麹菌に方向転換しちゃったんです。
以来、カテゴリー1は醸造のステージから退場させられてしまったんですよ。
新しい麹菌は変色しなくて卸しやすいうえに、酒粕の値段が倍以上になったこともあって、みんなカテゴリー2、3にいっちゃって……。本当は、カテゴリー1にしかできない味があるって、その頃の日本人も気付いてたと思うんだけど、やっぱり戦後の復興とか物がない時代の「みんなでいっぱい作って平均点上げよう」っていう中では、きっとこっちが大事だったんでしょうね。
- 一同
- へ〜〜!

- 古関
- 僕の師匠たちは80歳を超えて全員引退してますけど、存在そのものがかっこよすぎるもんだから、僕はそのおじいさんたちの技術こそが日本の伝統だと信じてきたんです。でも、じつはそれらは「枝分かれしたあとの技術」だったんですね。
で、話を元に戻すと、僕らが出会ったその「とある麹菌」というのが、じつは、カテゴリー1のなかで唯一生き残っていた麹菌だったんです。

- 古関
- この、カテゴリー1の麹菌、カテゴリー3と何が違うかというと、超強いんです。どのくらいって、もう「界王拳3倍くらい」の強さなんですよ!
- 一同
- ははは〜!
- 小倉
- だからむしろ、あまりにも強すぎる菌をどうやって抑えていって、自分たちの美意識に合う範囲のものに抑制していくかっていう。
- 古関
- そうなんです。強すぎると酒がくどくなっちゃうので。

- 小倉
- それ、ワインと一緒で、ワインってブドウの糖分を酵母菌が好きすぎて、放っておくとどこまでも発酵してしまうから、味がくどくなるんですよ。だから、醸造家っていうのは常に微生物と対峙するのね、ガチンコで。「気を抜くとあいつらに持っていかれる」みたいな。
もともとは僕たちが思っている以上に微生物は力が強いので、日本酒もそれに引きずられないように人間がいい感じに抑え込んでいくっていう造り方だったんだけど、いつしか人間が微生物そのものに使われるようになっちゃったから、自分の言うことを聞かない菌を排除して、そうじゃない菌だけを選んで品種改良するっていうスタイルになっていって……。

- 古関
- うんうん。
- 小倉
- それはそれで扱いやすくなったんだけど、その代わり、自分の想像を超える酒や発酵食品は作りにくくなったっていうのもある種の真理かもしれない。
- 古関
- カテゴリー1には、お米を溶かすことに関与する遺伝子が全部で21種類くらいあるんですって。ところが、カテゴリー3には7個しかない。その、14個足りない菌を僕らは原点だと思って使ってたんですね。つまり化学の話でいうと7個あれば十分なんですよ。
- 小倉
- うん。
- 古関
- だけど、カテゴリー1で造った酒は、いらない14個が何かしてるんですね。そして、理屈じゃなくうまいんですよ。

- 小倉
- ちょっと、まちづくりの話、してもいいですか? 全然関係ないんだけど、一応繋がってて。「都会で広告代理店でバリバリやってました!」とか「コンサルバリバリやってました!」みたいな人は、田舎に行くと、いきなりなんかすごい野性的になるというか。
「何でもやるぜ!」みたいな。農業もやるし、コンサルもやるし、Webも作るし、おばあちゃんの相手するし……そうやって覚醒することあるじゃないですか。
- 古関
- うんうんうん!
- 小倉
- なんか、都会の若者ってカテゴリー3の麹みたいなんだけど、田舎行くといきなりカテゴリー1になって、眠ってた14の遺伝子がいきなりパカッと開いちゃったりする。

- 古関
- それ、すっごいね! うちの蔵でやってるの、まさにそれなんですよ。「未熟は悪じゃない」っていうのがうちのキーワードなんだけど、初心者とか、感じ悪いやつとか、良いやつとか、いっぱいいるけど(笑)、まずは「そのまんまの姿でお前がいるのがいいんだから、お前の感じたまま喋れよ、感じたまま仕事しろよ」っていう……。鎧を剥がしてあげると、人が光り始めるんですよね。
- 小倉
- うんうん。
- 古関
- 「自分はちょっといまいちイケてないから。自分がわーってやるとみんな引くから」って言って、14個の遺伝子を1個ずつ殺してきた……僕もそうですよ。
- 小倉
- うん。

- 古関
- だけど、酒造りの場で「お前仕事できないよな」っていうのを肯定して「それでもここにいていいよ」って言うと、眠ってた14個の遺伝子のどれかが起きてくるんですよね。そうすると、なんか僕にできないすごいことするの。
- 小倉
- うんうん。
- 古関
- ……金八先生っぽいな(笑)。
- 小倉
- 野良菌なんだよね、このカテゴリー1ってやつは。「あるものに特化してない代わりに、いろんな力を使える」みたいなやつなんだけど。これでお酒造ると基本的には結構ワイルドな味になるかなと思うんだけど、でも古関さんが造るお酒って、いわゆる「雑味が売りです」みたいなことじゃないじゃないですか? シュッとしてる。
- 古関
- うんうん。

- 小倉
- こういうドーベルマンみたいな菌を、どうやってこうシュッとした感じに、最終的に落とし込んでいくのか? そこ、すごく気になるんですよね。
- 古関
- 結局、僕は造り手として「おいしいか、おいしくないか?」っていう基準だけで考えてます。そのために研究や経験を重ねていて……。
- 小倉
- じゃあ、その「おいしさ」っていうのは、どういうまとまり感なのか……。

- 古関
- ちょっとわかってきたのは、酒の余韻。「体にいい余韻」っていうのがあって、人間が酒呑んだときに「おいしい」って感じるのは、それなんじゃないかと思うんですよ。心地よい、美しい酔い……いや、フィーリング……?
- 小倉
- もうちょっと聞きたいな。
- 古関
- 何て言えばいいんだろう……。さっき(対談記事1話)も出た、色っぽい余韻……? だめだ、答えられてない!ごめん……ヒラクさん、お願いします!

- 小倉
- いや、僕の方から言うとね、ワインに近いものを感じていて、ワインの素晴らしいところって、呑んでからの旅が長いんだよね。
- 古関
- あ~。
- 小倉
- 呑んだ瞬間は水みたいなんだけど、その後、華みたいな感じがぱっと開いて、香りの酔いみたいなのがブワッと広がって、辛味みたいなのがきて、最終的にはピート(泥炭)っぽい感じの余韻が残って、最終的には消えていく。
その、呑んでから「呑み下す」までの味の変化とか、感覚の開き方みたいなのがよく設計されてる。それはたまたま生まれたものじゃなく、それを何百年も積み上げてきたんだなっていうか。単純にうまいっていうんじゃなくて、トリップ感がすごくあって。

- で、この間、古関さんが造った酒を呑んだ時に、結構そのワインのそれに近いものを感じて。単純に喉に消えていかないっていう。最近の日本酒は、飲み口が華やかですっと消えていく「消え方の良さ」が大事にされてたんだけど、あの酒はなかなか立ち去らない。「なかなか帰らねえなコイツ」みたいな(笑)。
- 古関
- ちょっと化学の話をすると、消されていた14個の遺伝子の中に、舌が感じない「オリゴ糖」っていう糖分を作る遺伝子も入ってるんですよ。
- 小倉
- なるほど!
- 古関
- ところがカテゴリー3では、オリゴ糖をつくる遺伝子は消えている。オリゴ糖っていうのは人間の脳が「甘い」とは感じないんだけど、「味わいの厚み」として感じられるようなことをするんですよ。その14個の遺伝子の何かが味わいを作っていて、それが舌触りやテクスチャーになって長い余韻になったり……っていうのは、起こりうることで、カテゴリー1には、人間が「化学的にわからないけどこれが気持ちいい」って感じる何かがいるんですよ。

- 小倉
- あのね、世界トップクラスのDJに会うと、超いっぱいレコード持ってくるの。で、レコードって12インチと7インチのサイズがあるんだけど、7インチの方持ってくるのね。それが最高なんだって言って。
なんでかっていうとね、今、最終的にiTunesとかになってるのって、MP3っていうデジタルデータ形式の音源なんだけど、あれって人間の耳に聞こえる音で調整してるんだけど、7インチレコードって犬みたいに人間よりも耳がいい生き物にしか聞こえない音域がいっぱい閉じ込められているんだって。
- 一同
- へ~〜〜!

- 小倉
- 音として良いかどうかは別として、体感として気持ちいいから7インチレコードがヤバいって言ってて。カテゴリー1の話とすごく似てる。細胞レベルでしか感じられないような。
- 古関
- 「データにできないけど感じる」っていうのを入れられるかどうかが大事だよね。
- 小倉
- 必然性があって、CDとかMP3とかになって、みんなが聴きたい時に音楽が聴ける、みたいなことが今までは大事だったじゃないですか。でも、それもある程度行き渡って、面白いということはとりあえずわかった今、その面白さをもっと突き詰めたいとなったときに、捨ててきた昔のやり方っていうのが実はすごい快楽度が高いんじゃないかってことに気付き始めてる。
「日本酒っておいしい」って気付いた、僕らの次のステージは、やっぱりMP3じゃなくて7インチレコードに戻るっていうことなのかなって。

- 古関
- だからこそ、感性で仕事をすることが何より大切で。でもね、カテゴリー3を全部否定するわけじゃなくて、ならば「もっととんでもないカテゴリーの麹菌がないか探してみよう!」とか「カテゴリー3でバケモンみたいな酒を造っちゃえ!」ってのが新政のやり方なんですよね。
これから造り出される新政の酒は、僕のやってきたことの再現とかではなく、どんどん変化させていってほしいなと。「新しい新政のおいしさ」がどう表現されていくのか、本当に楽しみ。

次回は、お酒の世界から一変、米作りという新たな挑戦を始めた古関さんのお話を伺っていきます。