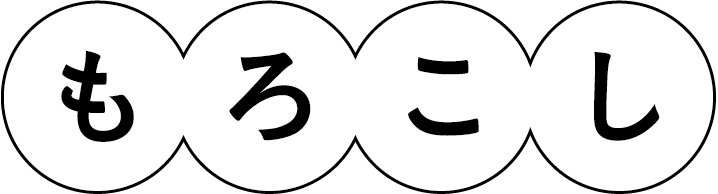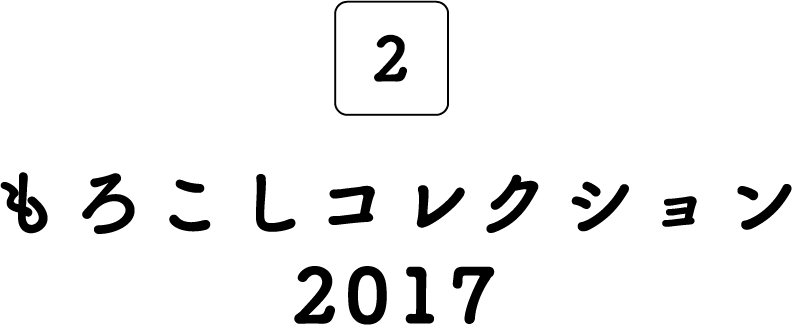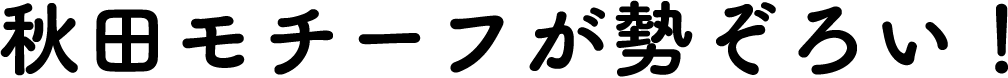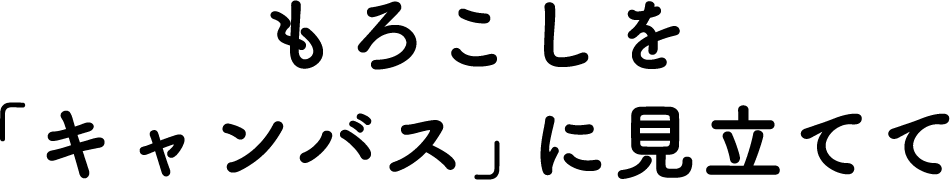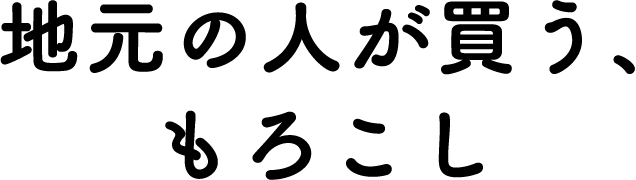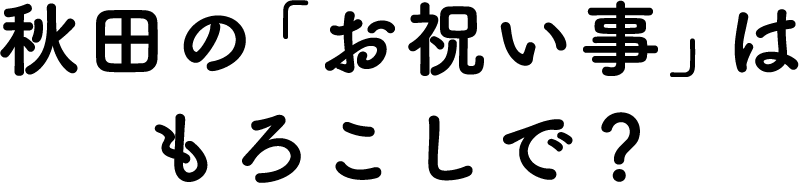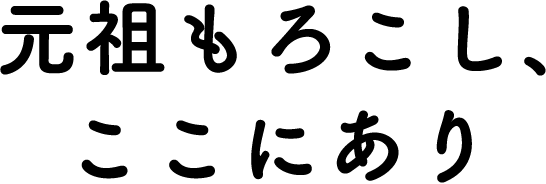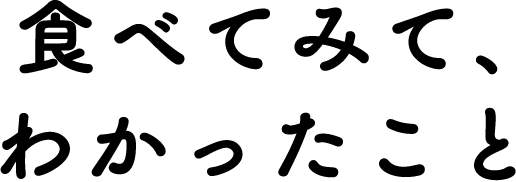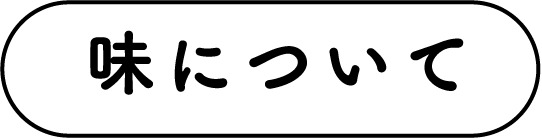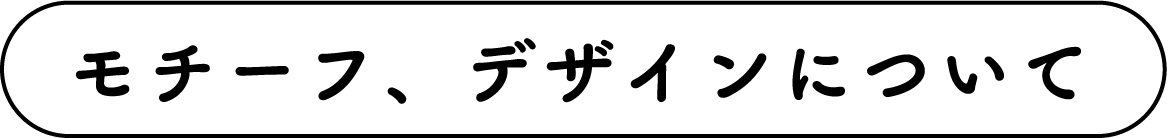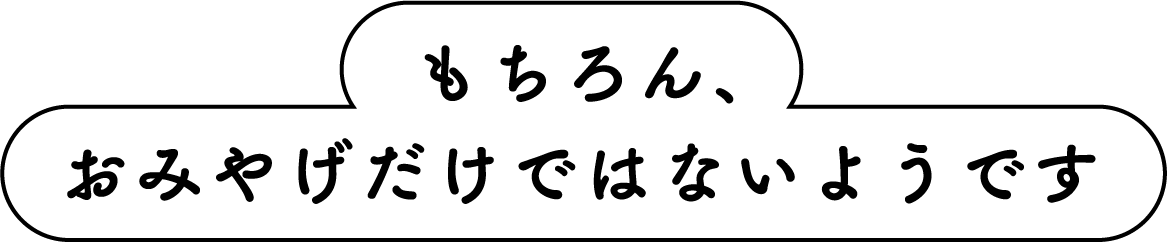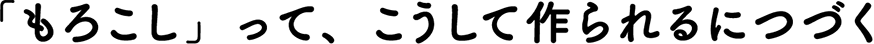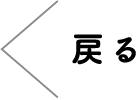前回、秋田市内を調査したものの、詳しい情報にはたどり着くことができなかった「もろこし」。しかし、市内のあちこちで買い集めたもろこしを並べてみると、実に個性的! 今回は、これらを一つずつ食べながら、もろこしについて調べてみます。
 謎に包まれた「もろこし」調査開始
謎に包まれた「もろこし」調査開始 「もろこし」コレクション2017
「もろこし」コレクション2017 「もろこし」って、こうして作られる
「もろこし」って、こうして作られる 秋田銘菓「もろこし」の未来は?
秋田銘菓「もろこし」の未来は?
文=高木沙織
富山県出身。関西14年ののち東京在住、3年目の編集者。秋田は初心者だけど「食」を中心に前のめりに開拓中。
わりとミーハーです。
写真=鍵岡龍門
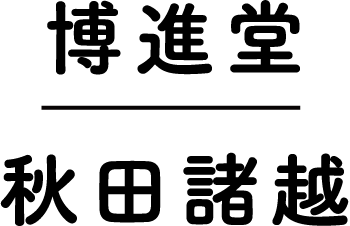
- 買った場所
- 博進堂


第1回で登場した博進堂のもろこし。なまはげ、竿燈に秋田おばこ(少女)、蓑をまとった雪ん子、湯沢市川連町で作られる木地山こけしなどの秋田モチーフが並びます。
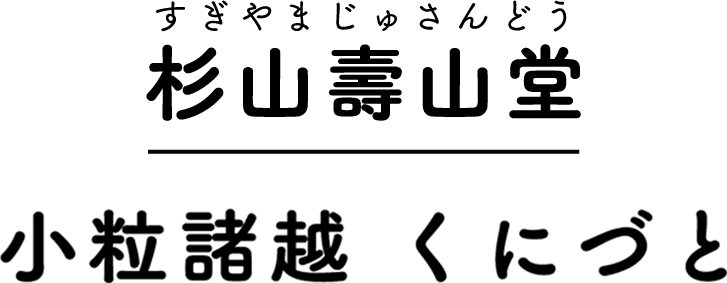
- 買った場所
- 秋田駅ビル「トピコ」2階

こちらも、なまはげ、秋田蕗、秋田おばこなど秋田モチーフが小粒でキュートに揃いました。キャンディーのように個包装されており、「おみやげ」の意味を持つという「くにづと」の名のとおり、まさに贈りたくなる品です。

- 買った場所
- アトリオン地下1階「県産品プラザ」


「男鹿」「十和田」などの観光名所や、「竿燈」「梵天」などの祭りをモチーフにした、素朴な彫り味がなんともかわいらしく心惹かれます。味違いの3色がパネル状に敷き詰められた様子も素敵。
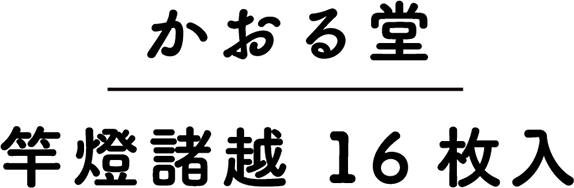
- 買った場所
- 秋田駅ビル「トピコ」2階


秋田のお祭り「竿燈」は焼もろこしに、名物「秋田蕗」は抹茶もろこしに。それぞれパズルのように組み合わせられています。大きさは長辺15cmほどで存在感たっぷり。
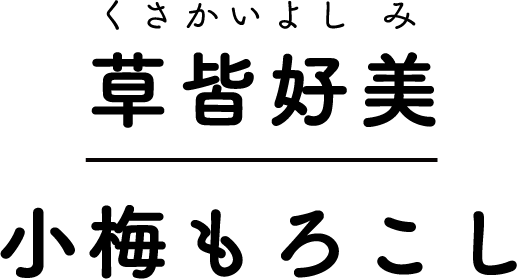
- 買った場所
- 秋田市内スーパーマーケット


小梅の形の焼もろこしは、五城目町で作られたもの。小さいので食べやすく、口どけの良い絶妙な硬さで、甘さもちょうどいい。日々の中で食べたくなるもろこしです。
※残念ながら7月末で製造をやめられるとのこと。
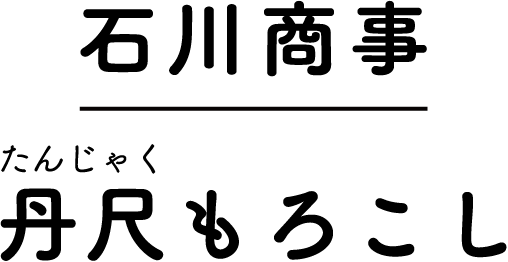
- 買った場所
- 秋田市内スーパーマーケット


ころっと四角い焼きもろこし。はっきりと配された「あきた」「もろこし」の文字が清々しい! 他と比べ、しっかりと硬さがあるのが特徴的。カリッと奥歯で噛みたい。食べ応えアリです。ちなみに、首都圏のスーパーマーケットにも多く出荷しているそう。
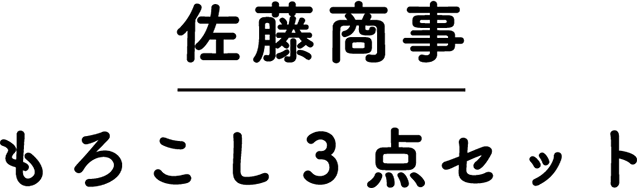
- 買った場所
- 秋田駅ビル「トピコ」1階 みんなの野菜畑



おめでたいシンボル、鯛・伊勢海老・亀の三役揃い踏み! 大きくて分厚い焼きもろこしは縁起物として飾って役目を果たした後は……やはり皆で食べるのでしょうか。
※ご購入には予約が必要となる場合があるそうです。
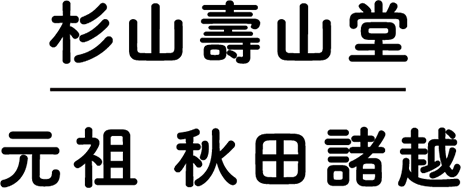
- 買った場所
- 秋田駅ビル「トピコ」2階


もろこしの元祖と言われる、創業1705年の杉山壽山堂。その屋号が型押しされています。
砂糖は一般的な上白糖に「和三盆」(四国東部で伝統的に生産される砂糖の一種。細やかな粒子が特徴)を加えています。
もろこしといえば、表面に焼き色が付いたものが定番と思われがちですが、焼き色を付けないものも口当たりが良く、好まれているようです。
焼き色のないものは、白色、きみどり色、むらさき色などとカラフル! 白色は「プレーン味(あずき粉と砂糖)」、きみどり色は「抹茶」がしっかりと感じられます。むらさき色は「あん粉」(あんこを乾燥させて粉にしたもの)を使用しているそうで、こちらもあんこの風味が生きています。
また、材料の砂糖に「和三盆」を加えた「元祖 秋田諸越」は、まろやかで上品な甘みを感じられました。
もろこしの基本の材料は、「あずき粉」と「砂糖」のみだから、そのシンプルさゆえ、素材が違えば味わいの変化も大きい。だからこそ、嘘をつけないわけですね。
もろこしのデザインは、「木型」次第で自由自在。だからこそ、もろこしをキャンバスに見立て、思い思いの絵を配置することだって簡単です。お菓子でありながら、工芸品のようにその造形を楽しめるのも、もろこしの魅力。そして、秋田モチーフ中心なのは、やっぱり「おみやげ」を想定しているからかもしれません。
市内のスーパーマーケットで購入した2種のもろこしは地元の人が買う商品でしょう。価格はほかと比べてリーズナブルですし、箱詰めではなく、ざっくりと袋に入った気取らない姿も、「日常のお菓子」そのものですね。
また、おめでたいモチーフの「もろこし3点セット」は、お祝い事にも重宝しそうです。筆者である私の地元の富山県では、結婚式の引き出物などお祝い事の際に、鯛の形をした大きな「かまぼこ」を贈る習慣があるのですが、それが、秋田の場合は「もろこし」になるのかもしれませんね。
今回ご紹介したのは、全県のもろこしのごく一部の商品にすぎません。それでも、秋田市内を巡っただけで、これだけのバリエーションが集まった、その「多様さ」こそが、秋田における「もろこし」の存在の大きさを表しているようです。

さて次回は、この「もろこし」がどうやって作られるのか、秋田市内の菓子店を訪ね、職人さんに工程を見せていただきます。