60枚の写真で振り返る
2018年の「いちじくいち」
2018年10月6日(土)・7日(日)に、秋田県にかほ市で開催されたマルシェイベント「いちじくいち」。【「北限のいちじく」を軸(じく)にして身の丈の豊かさについて考えられるような市(いち)】をコンセプトに、2016年、2…
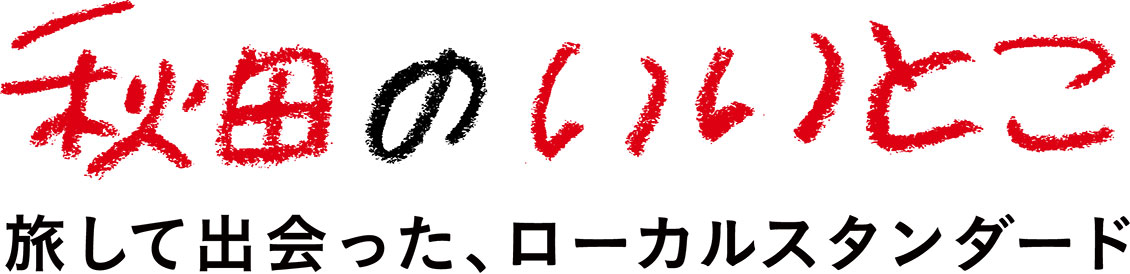

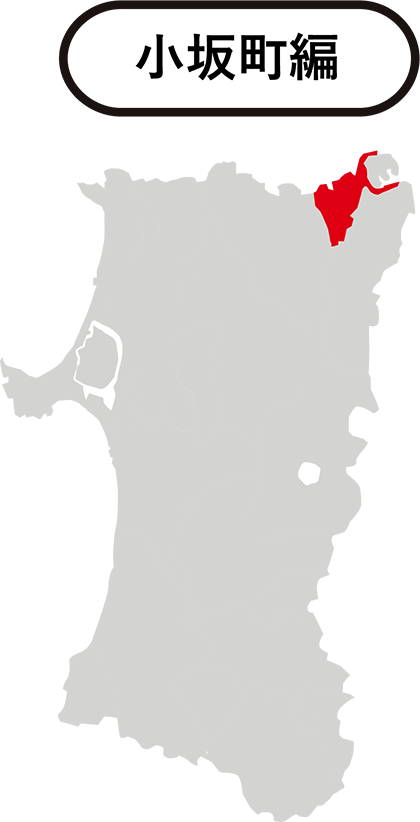
編集・文:矢吹史子 写真:船橋陽馬
2019.12.11
「テロワール」という言葉があります。これは、ワインの世界でよく用いられるもので、原料となるぶどうが育った、土壌や気候、生育環境などを総称した概念。
小坂町にも、このテロワールの概念のもと、ワイン製造をしている場所があります。それが、平成29年に誕生した「小坂七滝ワイナリー」。
今回は、この小坂七滝ワイナリーについて、小坂町グリーンツーリズム専門官の杉原隆広さんにお話を伺います。



——ぶどうの栽培や仕込みなど、全てをこの地域のなかで完結させたワインを作る、ということですか?

——すみません、私もわかりません。どう違うんでしょうか?








——山ぶどう系品種というのは、どんな特徴があるんですか?



——そんなに!?


——生産量はどのくらいなんですか?

——秋田はワインというよりは日本酒のほうが強い印象がありますしね。





——生産者さんは、いまどのくらいいらっしゃるんですか?




——となると、これからは、我々飲む側も成長していかないといけませんね。




【小坂七滝ワイナリー】
〈住所〉秋田県鹿角郡小坂町上向字滝ノ下22
〈TEL〉0186-22-3130
〈HP〉https://kosaka-7falls-winery.com/