一芯二葉。檜山の茶園主×神主。
能代市・檜山(ひやま)地区にある「元祖檜山茶大髙園(がんそ ひやまちゃ おおたかえん)」で生産されている檜山茶は、280年以上に渡って受け継がれてきた歴史のあるお茶です。「北限のお茶」としても知られ、商業生産されている日…
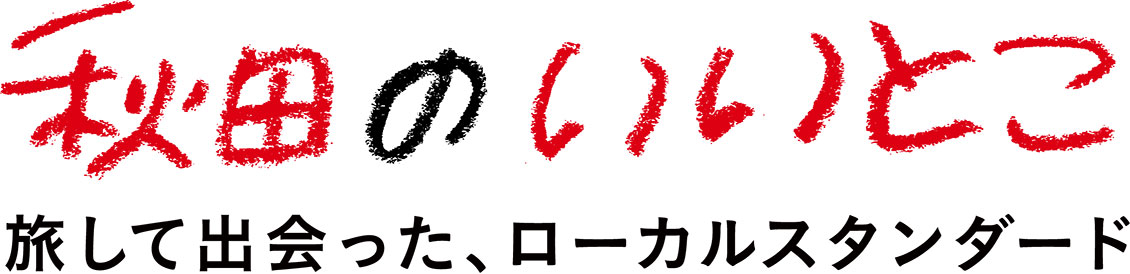

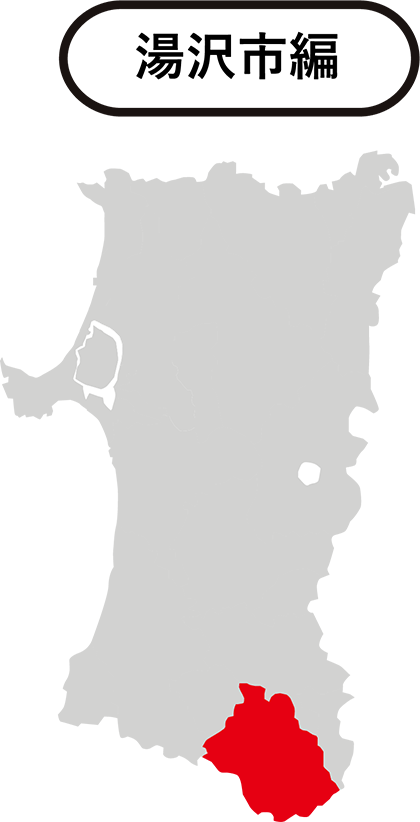
編集・文:矢吹史子 写真:船橋陽馬
2020.02.26
湯沢市にある会社「YAMAChuコーポレーション」。「地域活性化」「地域貢献」をスローガンに、地元食材を活かした食品を軸に、商品開発を行っている会社です。
……と、じつはこの会社、湯沢市立山田中学校が運営しているんです。そしてなんと、社員、役員、副社長、さらには社長までが、生徒によって構成されているというのです。
なんとも興味深い「YAMAChuコーポレーション」。その真相を確かめるべく、山田中学校を訪ねました。
はじめに迎えてくださったのは、教務主任の池田隆先生です。



——「商品開発をしたい」というのは、生徒たちのなかから出てきたアイデアなんですか?



——さすがに、この構造自体は学校側が考えたんですよね?

——素晴らしいですね! 商品開発はどんなふうに進めていくんですか?







——めちゃくちゃ楽しそうですね!


と、そこへ、2人の生徒がやってきました。



——今年はお二人はそれぞれ、どういうことをされたんですか?






——カレーのコピーにある「勝ち飯」というのはどういうことなんですか?

——実際、よく売れましたか?

——売れる喜びを感じられるのって、すごく大事ですよね。具体的に反響はありましたか?



——ご自身で「良い仕事したなあ〜」と思うのはどういうところですか?




——やっていると、学校に来るのが楽しみになるんじゃないですか?



——この会社を運営していくなかで自分が「成長したな」って感じることはありますか?



ここで、3年生の石川優人さんが加わります。商品開発部長、副社長として活躍してきた優人さん。今年は、地元麹店との味噌づくりにも力を入れてきたそう。
——ここまで、2年生のお二人から話を聞いていたんですが、このプロジェクトは、後輩との連携ができる場でもありますね。


——来年以降への期待も大きいのでは?


——「失敗ということはない」……含蓄のある言葉ですね。


——社長も生徒なんですよね? すごいなあ……。先生たちが生徒から学ぶということも多そうですね。

——この取り組みの目的は「地域活性」と伺いました。みなさんにとっての「地域活性」というのはどういうことだと思いますか?






——ないものを増やすことよりも、あるものを大切にしていく。空き店舗だって「使える可能性のある場所がある」とも捉えられますね。このような活動は、ほかの学校からも興味を持たれるのでは?


——全校生徒49名という規模だからこそできているんですね。



——最後に、来年度に向けての意気込みを聞かせていただけますか?




【湯沢市立山田中学校】
〈住所〉湯沢市山田字下館10
〈TEL〉0183-73-3017
【YAMAChuコーポレーション】
〈blog〉https://yamachu-co-ltd.hatenablog.com/