辞めるから始まることがある。
〜門脇光浩さん(前仙北市長)インタビュー〜
なんも大学編集長の藤本智士です。突然ですが、2016年から6年ものあいだ続けてきた「なんも大学」は、この記事をもって更新を終了します。世の中の状況がさまざまに変化していくなか、僕自身もいろんな思いが交錯し、次のフェーズに…



 椅子の向こうに見る景色
椅子の向こうに見る景色 あふれんばかりの、冷めることなき愛。
あふれんばかりの、冷めることなき愛。 精巧精緻・愛嬌満載
精巧精緻・愛嬌満載 不妊治療の未来を変えるために
不妊治療の未来を変えるために 「TO〜」あなたは何を描く? ビール、料理、建築の「TO〜MART」オープン!
「TO〜」あなたは何を描く? ビール、料理、建築の「TO〜MART」オープン! なくてもいいもの?
あきたタウン情報がつくってきた、たくさんの「きっかけ」。
なくてもいいもの?
あきたタウン情報がつくってきた、たくさんの「きっかけ」。 見えない物語を魅せる。アウトクロップ・スタジオ、始動。
見えない物語を魅せる。アウトクロップ・スタジオ、始動。 アニメの現場改革を、秋田から。
アニメの現場改革を、秋田から。 あなたを死なせない。「秋田モデル」が守るいのち。
あなたを死なせない。「秋田モデル」が守るいのち。 誰かの「こうしたい」に寄り添って。あくび建築事務所。
誰かの「こうしたい」に寄り添って。あくび建築事務所。 甘酒が咲かす、糀のチカラ。あまざけらぼ。
甘酒が咲かす、糀のチカラ。あまざけらぼ。 ブレンド米という知られざる世界への誘い。
ブレンド米という知られざる世界への誘い。 いつでも竿燈を楽しむひとつの方法。
いつでも竿燈を楽しむひとつの方法。 もっきり天国、土崎で100年以上続く酒屋を教わりました。
もっきり天国、土崎で100年以上続く酒屋を教わりました。 大森山動物園のいいとこをいくつもあげていきます。
大森山動物園のいいとこをいくつもあげていきます。 まさにノーミュージックノーライフ。 ホソレコで音楽再発見。
まさにノーミュージックノーライフ。 ホソレコで音楽再発見。 コーヒー&カセットのマイペース。
コーヒー&カセットのマイペース。編集・文:矢吹史子 写真:高橋希
2020.09.30
全国的にも深刻な問題とされている自殺対策。秋田県は、かねてから自殺率(人口10 万人当りの自殺者数)が高く、全国ワーストワンの時代が続いてきました。しかしながら、ここ数年で自殺者数は大幅に減り、ピーク時からは63%もの減少を見せているといいます。
このような要因の一つとして「あきた自殺対策センターNPO法人蜘蛛の糸」という機関の貢献が大きくあるといえます。
今回、このセンターを訪ね、その取り組みや考え方について理事長の佐藤久男さんにお話を伺いました。


——日本全体の自殺者数はどのような状況だったのでしょうか?

——どういうことが影響していたんでしょうか?



——男鹿市に暮らす人がそのままいなくなってしまうくらいの人数。

——秋田県の自殺者数のピークはいつ頃だったのでしょうか?


——今はその半数以下に減っているんですね!


——具体的には、悩みを抱えた方がこちらへ相談に来られるんですか?

——病院の窓口で体調を伝えて「では何科へ」と案内してもらえるような。こういう機関というのは、全国にもあるのでしょうか?


——これまで日本にはなかったものを秋田県では実践しているんですね。実際、年間どのくらいの方が相談に来られるのでしょうか?

——どういう相談が多いのでしょうか?


——普通にあり得る話ですよね。この場合は、どんなアドバイスをされるんですか?

——解決方法を具体的に示してもらえるんですね。

——そんなふうに、組織的に解決していくために、いろんな業態の方が仲間になっているんですね。



——「自分の悩みなんてわかってもらえない」「こんなこと相談していいんだろうか」と手前で考えてしまいそうですが、受け皿がしっかりとあるのであれば相談してみたくなりますね。


——悩みが積み重なっていく期間があるんですね。


——佐藤さんがこの機関を立ち上げたことには、何かきっかけがあったのでしょうか?

——ご自身も大変な時期だったわけですよね。何が佐藤さんをそこまで突き動かしたんでしょうか?





——コロナ禍で、経済的にも精神的にも不安定な方も増えてきていると思いますが、その対策などもされているのでしょうか?


——鎌田さんは、いつ頃からこちらに?
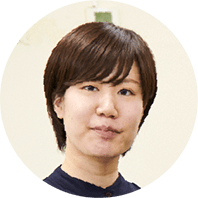
——8月からスタートして2ヵ月弱、どのくらいのLINE相談がありましたか?
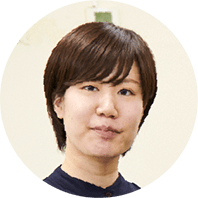
——直接面談に来るというのはやっぱりハードルが高いので、LINEで相談できるのは嬉しいですね。
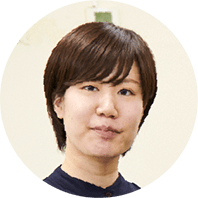

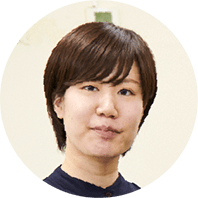
——第三者に客観的に見てもらうことが大事なんですね。

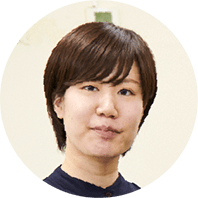
——どういう要因が多いのでしょう?
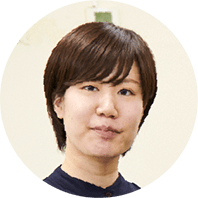
——いまは、SNSでの批判や攻撃というのもどんどん激しくなっていますよね。
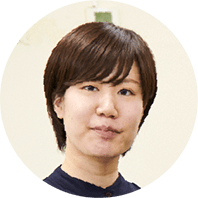
——若い世代とのやりとりを通して、感じられていることなどありますか?
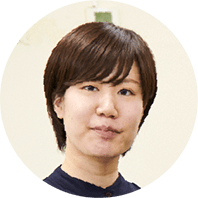




——まだまだやるべきことがたくさんありますね。


【あきた自殺対策センターNPO法人蜘蛛の糸】
もしもいま、つらい気持ちを抱えていたら
遠慮せずに私たちにお話をきかせてください。
もしも身近に、悩んでいる方がいたら
相談できる場所があることを、伝えてあげてください。
〈住所〉秋田市大町三丁目2-44 恊働大町ビル3F
〈TEL〉018-853-9759
〈HP〉https://www.kumonoito.info/
〈LINE相談ID〉156uujqi
